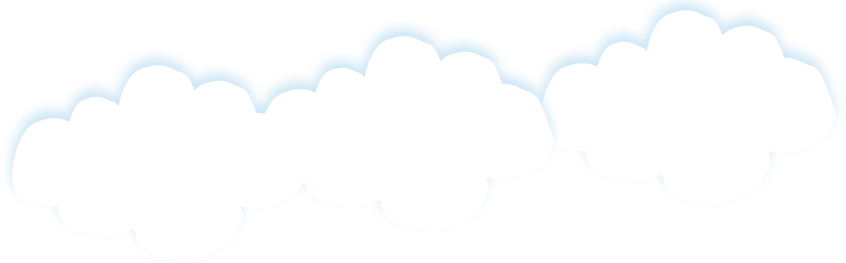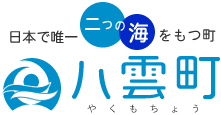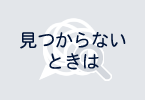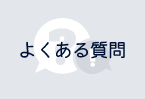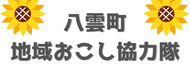【第16回】 再生可能エネルギーについて~水力発電~
今回は、「水力発電」について説明します。
水力発電は、水の流れる勢いや、水が高いところから低いところへ落ちる高低差を利用して発電機に繋がった水車(タービン)を回すことで電気をつくる方法です。
主な発電方法としては、水をせき止めるダムを建設し、河川の水位を上げて落差を得て発電する「ダム式」や、河川上流に取水堰を設けて落差が得られるところまで水を導き発電する「水路式」、ダム式と水路式を組み合わせた「ダム水路式」の3つの構造に分類されます。
再生可能エネルギーの中でも、エネルギー変換効率(作ったエネルギーを電気に変換した割合)が約80%と最も高く、自然条件に左右されず、昼夜を問わずに年間を通して安定的に発電を行うことが可能です。山が多く、水資源に恵まれた日本においては適した発電方法で、現在の日本の再生可能エネルギーの電源構成の約8%を占めており、発電のときに温室効果ガスを排出することはありませんので、クリーンな発電方法といえます。
しかし、ダム式の場合は、新規建設費用が高額であることや、広い地域を水没させる必要があることから、周辺の自然環境や生態系に悪影響が出る恐れがあります。また、降水量が少なくなると貯水量も減ってしまい、天候の影響を受けて発電ができなくなるという懸念事項もあります。
近年は、発電出力が比較的小規模ですが、大規模な河川が必要なく、自然環境への影響が少ない安価な管理コストで導入することができる「小水力発電(主に水路式)」の活用が注目されています。
2030年度までに温室効果ガス排出量を48%削減、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロの脱炭素を目指すためには、他の再生可能エネルギーと併せて検討が必要なものとなることから、地域の理解を得ながら導入の可能性を探っていきます。
↓過去の配信内容について
第1回~第15回