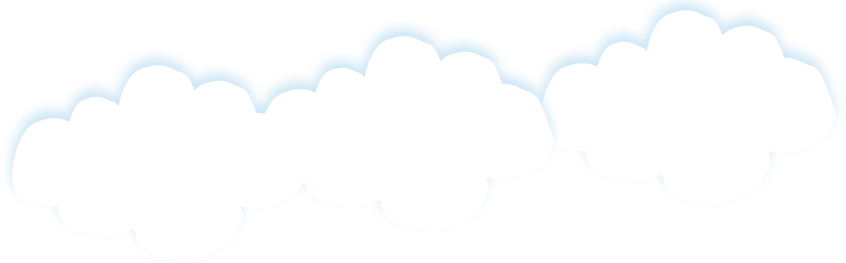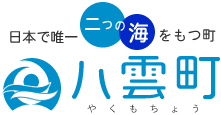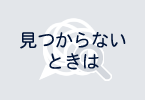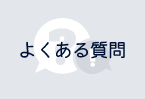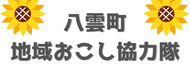児童手当
手当の趣旨
(児童手当法第1条・2条より)児童手当は、「家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的」としています。
児童手当の支給を受けた方は、児童手当の趣旨に従って用いなければなりません。
支給対象となる児童
次の要件を満たす児童について、手当が支給されます。
- 日本国内に住所を有する
(留学などで一時的に日本国内を離れている児童は支給対象) - 高校生年代までの児童
(18歳に到達後最初の3月31日まで) - 施設入所等児童でない
(詳しくはページ中部をご覧ください)
受給者となる方
八雲町に住所を有し、対象となる児童を養育している方。
要件については次のとおりです。
| 父母の場合 | 支給対象となる児童に対し、「監護している・生計が同一である」必要があります。単身赴任や進学等で別居している場合は、児童を監護し生計が同一であれば、対象となります。(申立ての手続きが必要です。) 父母がともに該当するときは、所得・保険の扶養・税の扶養状況などから総合的に判断し、受給者を決定します。 |
|---|---|
| 父母が離婚協議中の場合 | 支給の対象となる児童と同居している方に支給されます。手続きが必要です。 |
| 父または母がDV被害者である場合 | 支給の対象となる児童と同居している方に支給されます。手続きが必要です。 |
| 養育者の場合(祖父母等) | 父母と同一の要件(監護している・生計が同一である)で手当が支給されます。 |
| 未成年後見人の場合 | 父母と同一の要件(監護している・生計が同一である)で手当が支給されます。法人の場合は、事務所所在地が日本国内であることが必要です。手続きが必要です。 |
| 父母指定者(支給対象の子どもの父母が国外にいる)の場合 | 父母と同一の要件(監護している・生計が同一である)、および同居している方に手当が支給されます。手続きが必要です。 |
| 施設等に入所している子どもの場合 | 施設等の設置者に対し手当が支給されます。詳しくはページ中部をご覧ください。 |
※監護とは、子どもの生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っている状態をいいます。
手当について
手当月額
| 年齢 | 区分 | 1人当たりの月額 |
|---|---|---|
|
0~3歳未満 |
第1子・第2子 | 15,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
| 3歳以上~高校生年代 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 |
※第1子等の数え方は、22歳の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
例:令和6年4月1日時点で、20歳、17歳、14歳の子どもがいる場合
- 20歳 第1子 なし
- 17歳 高校生 第2子 月額10,000円
- 14歳 中学生 第3子 月額30,000円
支給日
定時払い 2月、4月、6月、8月、10月、12月の各月10日(土日・祝日の場合は、前営業日)
※支給日の前月までの2ヵ月分が、指定された口座へ支給されます。
随時払い 各月20日(土日・祝日の場合は、前営業日)
※転出による資格喪失など、定時払い以外の支払いが必要であるときに限ります。
施設入所等児童とは
「施設入所等児童」とは次のとおりです。これらに該当する児童は、父母等ではなく、施設の設置者が手当を受け取ります。
次に委託されている児童
- 里親
- 小規模住居型児童養育事業
次の施設に入所・入院している児童
- 障害児入所施設
- 乳児院
- 児童養護施設
次の施設に入所している児童(通所・短期間の入所を除く)
- 情緒障害児短期治療施設
- 児童自立支援施設
次の施設に入所し、児童のみで構成する世帯に属している者(短期間の入所を除く)
- 救護施設
- 更生施設
- 婦人保護施設
- 障害者支援施設
- のぞみの園
児童手当の認定請求について
児童手当を受け取るためには、「認定請求書」の提出が必要です。
児童(1子目)が出まれた場合
出生日から15日以内に認定請求の手続きを行ってください。出生日の翌月分から支給されます。15日以内に手続きを行わなければ、請求日の翌月からの支給となります。
※出生届の提出だけでは、児童手当は支給されませんのでご注意ください。
八雲町に転入される方
前住所地の転出予定日から15日以内に認定請求の手続きを行ってください。転出予定日の翌月分から支給されます。15日以内に手続きを行わなければ、請求日の翌月からの支給となります。
※転入届の提出だけでは、児童手当は支給されませんのでご注意ください。
公務員をやめた方
退職日から15日以内に認定請求の手続きを行ってください。
認定請求手続きに必要なもの
- 請求者名義の通帳の写し
- 請求者のマイナ保険証の情報を確認できる書類もしくは資格確認書の写し(社会保険に加入している方のみ)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者、配偶者、児童)
- 身分証明書(個人番号を提出した際に必要)
写真付き身分証明書の場合は1点(運転免許証、パスポート等)
写真無し身分証明書の場合は2点(住民票の写し、年金手帳等)
(以下の書類についても必要になる場合があります。)
- 別居監護申立書(受給者と対象児童が住民票上、住所が異なり、別居している場合)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(18歳年度末以降22歳年度末までの子を含めて3人以上の児童がおり、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ生計費の負担をしている場合)
児童手当受給中に必要な手続き
児童手当を受けている間、次のようなときは手続きが必要です。
変更等の手続き
・支給対象児童が増えた場合(新たに児童が生まれた、養育する児童が増えたなど)
・支給対象となる児童を監護しなくなった場合(離婚、児童の施設入所など)
・八雲町を転出する場合
・受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わった場合
・児童や配偶者と別居することになった場合(児童の進学や転勤など)
・受給者の加入する年金が変わった場合(受給者が公務員になったときを含む)
・金融機関を変更する場合
・18歳年度末以降22歳年度末までの算定児童の職業区分が変わった場合(学生から就職したなど)
その他手続きが必要な場合がありますので、変更等がありましたらお問い合わせください。
現況届について
毎年6月にご提出頂いていた「現況届」が令和4年度より提出不要となりました。八雲町では、公簿等で受給者の現況を確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし、支給要件児童の住民票が八雲町にない方等、現況届提出を省略できない場合があります。提出が必要な方は町より現況届提出の案内を致します。
また、令和6年10月の制度改正に伴い、4月以降も引き続き監護相当・生計費の負担がある場合は、児童手当の第3子算定に含めることができます。監護状況について確認する必要があるため、手続きが必要な方は町より案内を致します。
児童手当からの保育所等利用者負担金(保育料)の徴収について
児童手当受給者の申出による徴収
各認可保育施設に係る利用者負担金の全部または一部を、児童手当から直接納付することが可能です。希望する方は、次の窓口まで申し出ください。(公務員の方は対象外です。)
例)保育園に入所している子ども(3歳未満)が1人いる児童手当受給者の場合
令和6年12月期定時払い 予定額30,000円 利用者負担金月額13,600円(所得により金額が異なります)
→利用者負担金令和6年10月~11月分の2か月分27,200円を児童手当から支払い、差額2,800円を児童手当として受け取る
申請期限
児童手当各支払月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の前月15日まで
申請先
- 住民生活課児童係(窓口5番)
- 熊石総合支所住民サービス課
- 落部支所
問い合わせ先
住民生活課児童係(電話:0137-62-2112 内線245)
児童手当からの特別徴収
保育料を滞納している児童手当受給者の場合、八雲町の判断により、児童手当法に基づき児童手当から滞納保育料を徴収します。対象となる方には、各支払月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に通知します。
問い合わせ先
住民生活課児童係(電話: 0137-62-2112 内線245)
寄附制度
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを八雲町に寄附し、子ども・子育て支援事業のため、活用してほしいという方は、簡単な手続きで寄附を行うことができます。
手続きをされる場合は、身分証明書をお持ちください。
受給額証明の発行について
奨学金申請などで必要な児童手当受給額証明について、支払い通知(はがき)を紛失した場合には証明書を発行いたします。身分証明書を持って窓口までお越しください。
手続き窓口・お問い合わせ先
住民生活課児童係(窓口5番)
電話:0137-62-2112(内線245)
熊石総合支所住民サービス課
電話:01398-2-3111
落部支所
電話:0137-67-2231