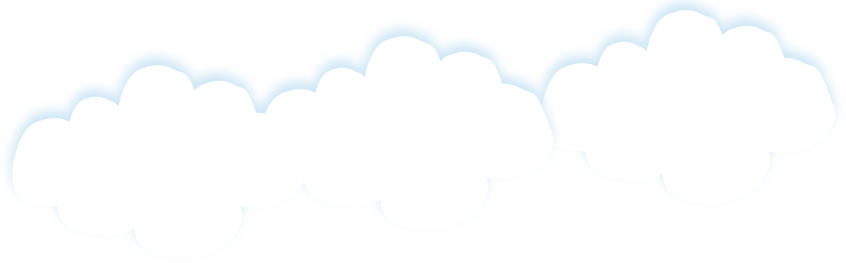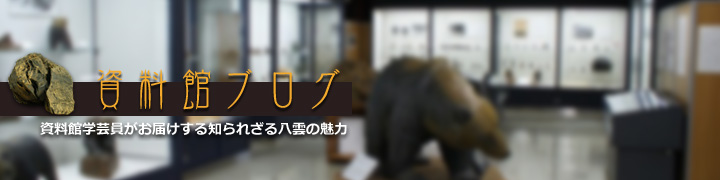上ノ国町の旧笹浪家住宅(重要文化財)横にある、嘉永元年築造の「米・文庫藏」で、「平成22年度 笹浪家企画展 蠣崎氏と松前氏」(10.16~11.14)が開催されていました。その中に「松前町教育委員会所蔵(村岡チヤ氏寄贈品)」として、弁開凧次郎家使用品の天目台3点、イクパスイ2点、角盥1点が展示してありました。
参考に、展示プレートの文章を紹介します。
「弁開凧次郎さんとは?」蝦夷地落部出身で、アイヌ名をイカシバという。明治~大正時代の家畜商。明治35年(1902)、青森県八甲田山で陸軍の兵隊210人が猛吹雪にあい、このうち199人が死亡するという事件の際には、9人のアイヌが救助に向かい、弁開氏が隊長を務めた。また、馬など動物の治療にも精通し、地域の人々に大変したしまれたという。
「角盥(つのたらい)」本来は和人のお歯黒道具や洗面道具のひとつであるが、アイヌの人々は、儀礼の際に供物などを入れる容器としても用いた。
「イクパスイ」儀礼用具のひとつで、酒を神に捧げるときに使う木べら。イクパスイは、人間の言葉の足りない部分を補い、誤りを訂正し、雄弁に神に祈りを伝えてくれるといわれる。展示品は、シャチやクマなどが彫られている。
「天目台(てんもくだい)」もともと日本の茶道では天目台に陶磁器の茶碗が載せられたが、アイヌは漆塗りの椀を載せるという独特の使い方をした。天目台と漆器のセットを一客としたものをトウキといった。儀礼の際には漆塗りの膳に四客のトウキを置き、それぞれにイクパスイを載せる。

旧笹浪家の米・文庫藏

弁開凧次郎家使用品
投稿者:しんちゃん