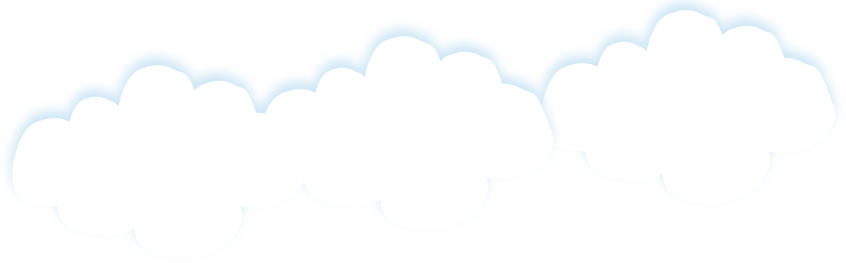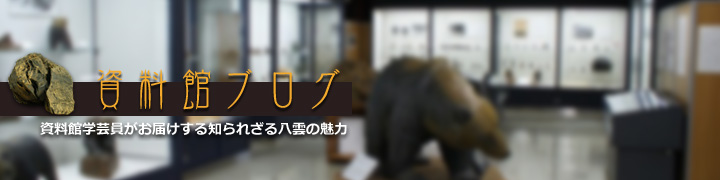先日、東京より研究者が訪れ、山越の臭水油”くそうずゆ”の現地調査を行いました。臭水油或いは臭水”くそうず”とは、石油の古名だそうです。原油が臭うことから”くさみず”の音が変化して”くそうず”となったそうです。
松浦武四郎の『東蝦夷日誌』には、山越内で臭水油が湧いているのを池田伊右衛門が発見し、皮膚の感染症である疥癬(かいせん)の膏薬(こうやく)を作って売っていたという記述があります。また、鳥もち(鳥や昆虫を捕まえるための粘着物)の代用品としたという言い伝えもあります。
明治2年に終結した函館戦争の首謀者であった榎本武揚は投獄されますが、黒田清隆の尽力により明治5年に出獄します。その後、人材を必要とした明治政府によって開拓使四等出仕に任命され、北海道の石油・砂鉄・石炭の調査にあたることとなり、山越の石油の調査も行ったとのことです。
円融寺の駐車場横にある、コンクリートで囲われた溜池では、生ぬるい水が湧き出て、水面には油膜が確認されました。近所の人の話では、以前、円融寺裏手では天然ガスが噴出し、燃料として使っていたという話を聞きました。山越郵便局の少し南側の国道沿いには、昭和3年頃に佐藤温泉という冷泉の出る旅館があり、昭和15年頃まで営業していたそうです。現地を歩いて、山越地区は地下資源の宝庫という感じがしました。
 |
 |
|
円融寺の駐車場横の溜池 |
国道5号沿いの溜池 |
 |
 |
|
側溝より湧き出る石油を含んだ水 |
佐藤温泉跡~の溜池(白く沈んだものは湯華とのこと) |
投稿者:しんちゃん