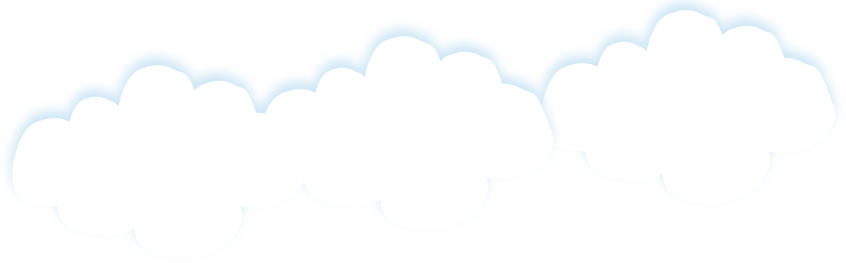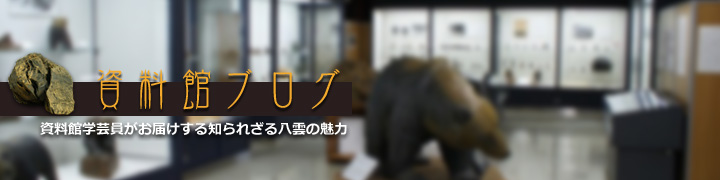郷土資料館に展示している鮭の剥製に関する新聞記事を発見しました。昭和53年1月の北海道新聞で、昨年末に水産庁さけ・ますふ化場渡島支場で、遊樂部川に遡上した鮭をふ化事業用に捕獲していたところ、体長約1m、体重12kgもある雄の5年漁で標準の鮭3匹分もある大きなものを捕獲したとのこと。剥製にして町に寄贈され、5月にオープン予定の郷土資料館に展示予定という記事でした。また同支場によると、本年度(昭和53年度)は秋から冬にかけて遊樂部川には史上最高の鮭の大群が回帰し、同支場と八雲漁協では4万匹近い親魚を捕獲したとのことです。
遊樂部川の鼻曲がり鮭は、江戸時代の文献にも記述があるとのことですが、乱獲による資源の減少を危惧した開拓使函館支庁が、明治13年に徳川家開墾試験場に鮭の天然種育蕃殖事業を委嘱し、新潟県の三面川(みおもてがわ)の天然ふ化の方法にならい、ふ化事業を行ったのが、八雲での鮭ふ化事業の始まりとされています。
ちなみに、鼻曲がりとは、鮭の雄が川を遡上するとき鼻先が伸びて先端が下に曲がる生理的変態だそうで、海水から真水に入るときになるそうです。
また、明治22年に徳川家の開拓移住人の自治基本法とも言える「八雲邨徳川開墾地郷約」が制定され、その第2章第6条に「移住人徳川侯ニ対スル義務」で、毎年徳川家に豆と鮭を献上することが義務づけられていました。戦後は、「献上豆」・「献上鮭」の献上という言葉が贈呈と代わり、現在でもその伝統は続いているそうです。

遊樂部川の鼻曲がり鮭の剥製
投稿者:しんちゃん