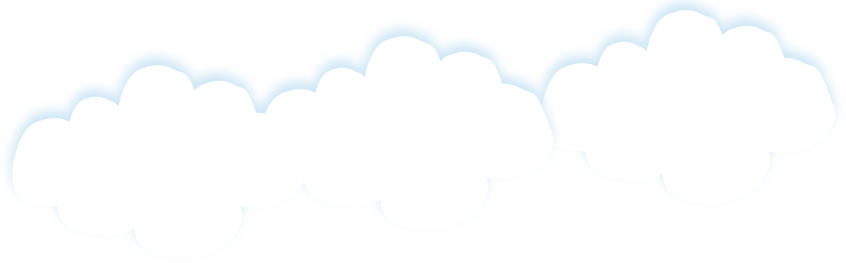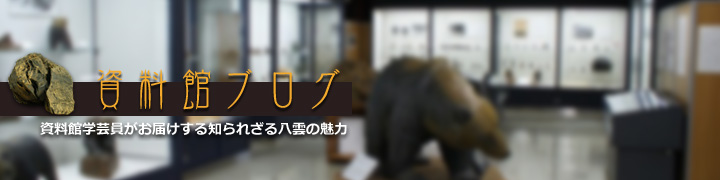平成23年5月25日の北海道新聞に、東日本大震災での「津波遡上高30m超8カ所」の記事がありました。津波遡上高とは、「津波が海岸に到着した後、さらに陸地をせり上がった高さ」と説明され、さらに寛保津波で34m、北海道南西沖地震では30.6mの津波遡上高があったと記されていました。
寛保津波とは、『福山秘府』によると寛保元年(1741)7月16日に日本海の渡島大島が大噴火し、同19日に松前弁天島から熊石村にかけて大被害をもたらした津波で、溺死者1,467人、家屋倒壊791戸、破船1,521艘の被害があったそうです。
「無量寺過去帳」によると、相沼内村では30人、泊川村では13人、熊石村では24名の死者があり、町内には、相沼の無量寺に供養碑があります。その他、松前町の光明寺と泉龍院に、江差町では正覚院と法華寺に供養碑があり、いずれも大津波の貴重な歴史的資料として北海道有形文化財に指定されています。

無量寺寛保津波の碑
延享3年(1746)に、津波犠牲者の七回忌に建立された地蔵座像で、背中には三個の穴が開いています。
投稿者:しんちゃん